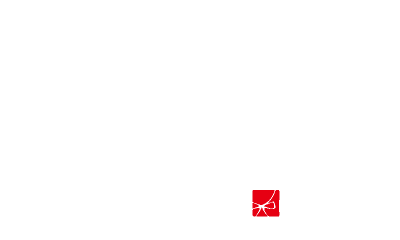韓国から日本へ
秋場俊雄は1962年に韓国・仁川で生まれた。家は貧しく、両親がいないため物心がついた頃には親戚の家を転々としていた。小学校は4年までしか通っていない。彼の弟や妹は小学校に入学することすら叶わなかった。その彼が日本に引き揚げる叔父たちと共に対馬海峡を渡り、下関を経由して東京にやって来たのは1974年11月のことである。当時葛西にあった引揚者向けの寮に弟妹たちと転がり込んだ。
12歳の秋場は翌年4月に中学校への入学を控えていた。だが、日本語がまったく話せない。外国に生まれ育った小学生が4ヶ月足らずで日本語をマスターすることなどできる訳がない。諦めかけたが、周りの勧めや先生たちの熱心な働きかけもあって、何とか入学を果たした。ひらがなは読めるようになったが、漢字はまだ読むことができない。国語の時間に指名され、席を立ち教科書の一節を読んだ。漢字を飛ばして平仮名だけを。それを聞いて周りの生徒は大笑いした。そしていじめが始まった。まるで珍しいものを触るかのように「お前、どこから来たんだ?」「なんで漢字読めないの?」とちょっかいを出す。右も左もわからない。習慣もまるで違う。毎日小突かれ笑い者にされた秋場は、「子どもながらに必死だった」と、当時を振り返る。
中学を卒業すると工業高校へ進んだ。普通科に行けるギリギリの成績だったが、手に職をつけろと担任に諭された。進学したものの、自分は油まみれになるのが性に合わないと気づき、その一方でコックに惹かれた。取り立てての理由はなかった。ホテルのフレンチでコックをやりたいと担任に話すと、それには専門学校へ行かないとダメだと言われた。もちろんそんな金はない。そこで、秋場は銀座ライオンの中華部門に就職した。給金をもらいながら料理の勉強ができると考えたが、料理人の現場は上下関係が厳しい。先輩に頭を叩かれ、毎日くたくたになりながら1年を過ごしたが、この職場は自分に合わないとやめてしまった。

料理で生きていく
気ままだが何もすることのない日々を過ごしていた秋場は、やがてコックの世界が恋しくなった。何が恋しかったのだろう? 聞くと「働いている実感」と言う。その「実感」を胸に、秋場は再び料理店に就職した。そして早朝から晩まで厨房を走り回った。皿を洗い、食材を運び、皮をむき、また皿を洗う。厨房の隅々まで磨き上げるのは、最後のオーダーが運ばれてから。仕事が終わるのは終電近くという毎日だった。こうして3年が過ぎ、22歳になった時に、この道で生きていこうと決心した。胸に志すものが芽生えていた。そして、それまで以上に料理に取り組んだ。脇目も振らずに。一心不乱に。
「仕事するって、どういうことかわかりますか?」
秋場が私に問いかける。いくつもの答えが浮かんだが、私の言葉を待たずに秋場が続けた。
「僕には帰る家がない/居場所がないから自分で居場所を見つけなければならない/日本に自分の居場所を作る/それが仕事」
居場所を作るためには腕に磨きをかけなければならない。ましてここは日本だ。頼る人もいない異国なのだ。
サッポロライオンを経て21歳で丸の内会館、25歳で上野の北京飯店、26歳で銀座四川と渡り歩き、28歳で頤和園に副料理長として入った。料理に関する知識を貪欲に吸収し、常に人の倍以上働いた。先輩でも違うと思ったら、面と向かって「ダメ」と言った。生意気だと罵られても気にしなかった。そして30歳で料理長になった。修行時代を含めて12年、身を粉にして働いてきた。ここで満足してもいいだろう。十分やってきたではないか。その結果としての料理長だ。だが、秋場は自分の腕を改めて振り返り愕然としたという。自分には1年分の「引き出し」しかないと。そして、多種様々な「引き出し」作りに、それまで以上に励んだのである。

引き出しづくり
秋場に「引き出し」とは何か? 作ることの出来る料理の数か、と聞くと、それもあるという。それもあるが、詰まるところ料理についての想いと考え方だと言う。例えば蕪。ひとつの蕪で30代、40代、50代、60代、70代の客に、それぞれどんな料理を味わって欲しいか、それをどのように作るかを、今は考えることができる。だが、若い時はこの蕪で何通りの料理が作れるか、それしか頭に浮かばなかったと。それが今では「いくつでも出てくる」と言う。
「例えば、お客様の顔色が良くない。聞くと、やはり体調を崩している。そこで、メニューをすべて変えるわけですよ。同じ食材で、味つけから食感までのすべてを」
秋場の真骨頂はオーダーメイドである。もちろんお任せに限るが、客の体調やテーブルを共にする人の構成を見て、内容をガラッと変えてしまう。まさに「あなたに合わせて」作る。その腕、秋場の言うところの「それを自分で作ってあげられる状態」には引き出しの数が必要だ。そして「その深さも」と笑う。引き出しの数という例えは耳にするが、深さについては聞いたことがない。「数」と「深さ」がある「引き出し」を、秋場はどのように手に入れたのだろうか?
秋場は、毎年のように中国大陸に足を運び、様々な料理を食べ歩いている。日本の中華料理はどうしても日本人の口に合うようにアレンジされているからだ。中国では、調理人自身が育った料理、郷土料理をそのまま調理し提供する。実にシンプルで、日本の中華料理とはまったく別物だと秋場は感心する。
気の向くままに街を歩き、気の向くままに料理屋のドアを開ける。見た目も味も違う料理はとても面白いと、口に合うかどうかは別にして食べ歩く。そうして出会った料理の印象をノートに書き、描いて記憶に刻む。食材、調理法、味つけ……。そして、この一皿を自分だったらこう扱う、こう調理すると想像し、手順まで考える。それを長年重ねるうちに、クラシックな定番料理から日本人には馴染みのない田舎料理まで、その作り方のエッセンスを身につけた。高級食材を使い、質の高い調味料で味つけするのもひとつの料理。ごく普通の食材を、シンプルな味つけで仕上げるのもひとつの料理。人や場に合わせて変化を交えながらの一皿を提供できる、底の深い引き出しをいくつも手に入れたのである。

料理について
秋場の料理を際立たせている手法に油の使い方がある。中華料理は油をふんだんに使い、仕上げにもごま油やネギ油、エビ油などを使い香りをつける。従って、皿に盛られた料理はどれも艶やかだ。一方、秋場は極力油を使わない。理由を聞くと「DNAが韓国なので脂っこいのがきつい」と冗談交じりに言う。確かに油が口に残ると、続く料理の味がぼやけてしまい、味わいを損なう。秋場は火に通すと酸化し、素材の味を濁らせる油を嫌う。そのため一品食材を湯通しする毎に油を湯で流す。鍋やフライパンを洗い、仕上げにはごく少量の新しい油を使い、香りをつける。手間がかかるが、こうして油のマイナス面をそぎ落とす。
様々な工夫も取り入れた。例えば「ラー油」の代わりに「ラー水」を使う。熱湯に鷹の爪を山ほど入れ、胡椒を加えて作る水の辛いやつだ。使うと辛味だけ残ってさっぱりした味になる。また、唐辛子とニンニクで発酵させた水は、炒めものの仕上げに使う。いずれも秋場のオリジナルだ。こうして油を極力落とした料理は胸焼けしない。自然と箸が進み、気がつくと、いつもより注文する皿の数が多くなっている。食べ終わった皿には、ほんの少しの油が残るだけだ。誰もが和食に近い味わいだと感心する。
定番のチャーハンは米一粒にこだわった。火を入れてパラパラになる卵を飯粒と同じ大きさに揃える。すると、均一に散りばめられた卵が黄金のように輝き鮮やかだ。また、飯粒の表面に塩の粒がつくことを嫌い、仕上げに温かいスープを鍋肌にほんの少し流し込む。その蒸気で塩が溶け飯粒の中に染み込み、と同時に油も入る。これをタイミングよく配膳することで、客の目の前に置かれた皿から湯気が立ち上る。ふぁーっと温かく、馥郁たるチャーハンの香りが鼻を刺激する。まさに作り立てで、まさにチャーハンを待っていた自分に作ってくれたのだとの思いが伝わり嬉しくなる。しかも、食べることがもったいなくなるほど美しい。食べると口当たりが甘く柔らかだ。コシヒカリの旨さもしっかり味わえる、実においしいチャーハンだ。
ナスの唐揚げも秋場のオリジナルだ。ナスは焼いたり煮たりが一般的だ。揚げるのも素揚げ止まりだろう。秋場はナスの皮を剥き、塩と胡椒で揉んで少し柔らかくし、小麦粉と片栗粉を水に溶き、それに茄子を潜らせ低温でゆっくり揚げる。すると表面がパリッとして、カリッと揚がる。見た目はまさに唐揚げだ。知らずに食べると、誰もが不思議そうな顔をすると言う。これ何?
ユニークでおいしい料理を作るのは、持って生まれた才能なのか、それとも鍛錬なのか、それとも……。自分は天才ではないと秋場は言う。何かあるとすれば、それは想像力ではないかと。
「自分が見たもの、聞いたもの、食べたものの中から、あれとこれを組み合わせたらこうなるかなと常に想像し、考えます。」
その想像力の賜物のひとつが「秋刀魚の春巻」だ。秋刀魚を3枚におろし小骨をすべて取り、酒、塩、胡椒を少々まぶして蒸す。身がぷるんとしておいしいが、そこ止まりでは面白みがない。ここで想像し、考えるのは、どうやって秋刀魚の香りをつけるかだ。魚の香りは内臓にある。まず肝をすり潰してスープでのばし、そこにニンニクを入れて臭みと苦みを取りながらソースを作る。そのソースを片栗粉で固めにしめる。それを春巻きの皮に塗る。秋刀魚の身を挟み、皮で巻いてゆっくり揚げる。すると中の硬いソースがじっくり溶けて秋刀魚の身にしみ込んでいく。7〜8分かけて揚げると皮がパリパリになる。夏場は鮎を使い、秋から冬は秋刀魚を使う。
こうしたヒントは自分の「引き出し」以外に、人の口からひょっこり出ることもある。話を聞きながら秋場は想像する。それを使ってこうやるとどうだろうか? あの料理に使うとおいしいかも……。中国での食べ歩きで身につけたテクニックを使う。だから100%クリエーティブな作業じゃないと謙遜する。とはいえ、どこにも存在しない、まったく新しい料理を作るのは、太洋に落ちた指輪を探すようなもの。誰もが唸り、感心し、笑顔になる料理を前にすれば、それは取るに足らぬものだろう。

手間を惜しまず料理に向き合う
手間を惜しまず
料理に向き合う
最後に「料理はひと手間かけないとダメ」と秋場がつけ加えた。
刺身を買ってきて、パックのままテーブルに出すのか、キレイな皿に盛りつけて出すのか、その違いは大切だと言う。皿に盛りつけても盛りつけなくても味は同じ。でも、それを惜しむと料理ではなくなってしまう。
例えば夏場に、冷やし中華じゃなくて冷やしラーメン作ってと注文が入る。面倒だな、と思いながらも「いいですよ」って作る。タレはすぐできる。さて、麺をどうするか? ボイルして麺がつるんとすれば出来上がり。そのまま出してもいい。だがちょいと待てと、ここでもうひと手間加えようと。茹でた麺を洗って、もう一回さっと茹でる。こうすると、麺の喉越しが格段に良くなる。これが手間暇をかけること。秋場はそれがおいしさの前提になってくる。
それはそうだが、手間はコストである。おいしい料理を味わって欲しいと手間をかければかけるほど店の売り上げは減り、料理人は消耗する。このバランスは、料理店にとって常に悩ましいものだ。この点、秋場の答えは明快だ。
「バランスは考えません。あくまで料理屋ですから、自分ができる最高のパフォーマンスをすべてお出しします」
手間暇は愛情と同じ。時間的な原価はかかるかもしれないけれど、自分たちが苦労すればそれで済む話だと、秋場は笑う。私は2回3回と頷き、そして理解した。秋場には客に対する「想い」が常にあるのだろう。何かしらの「想い」がなければ愛情は生まれない。愛情が手間暇をかけさせるのだ。そうした「想い」を持つ料理人に、私は今までに出会ったことがあるだろうか?
それはともかく、秋場の料理に出会うことは、素晴らしい体験になることは間違いない。そう、できれば一度味わって欲しい。それが彼と語り合った私の「想い」である。

インタビュー・文:篠塚 順(JQR編集長)
https://jqrmag.com/